こんにちは。
はじめまして、オイジーです。
この度は足を運んでいただいてありがとうございます。
どんな人間が記事を書いて、なんでワインを提案しているのか。
気になる人もいるんじゃないかと思ったんですよね。
それにこのタイミングを逃すと今後自己紹介することもないんじゃないかと思い、書いてみることにしました。
「Oisy」で「オイジー」
「Oisy」と書いて「オイジー」と読みます。
「オイシー」ではありません。
私が働く「Noisy Wine」の店主が「ノイジー」です。
私はノイジーの甥(おい)にあたるので、「オイジー」となりました。
とあるお客様につけていただいたんですが、
「おいしい」にも掛かってるし、なんだかんだと定着して、今では割と気に入っています。
どんな人間なのか
恐らく、自分で自分のことを正確に説明できる人はいないのではないか、と思うんですね。
少なくともオイジーはそこまで客観的に自分のことを見れないと思います。
なので、いままで、どんなことをやってきたのか
ということを羅列してみようと思います。
なにをやってきたのか
意外かもしれませんが、学生時代は和食を専攻して、学んでいました。
実際はイタリアンをやりたかったのですが、
和食を知らんで他の国の料理を学ぶのも違うような気がするし、
なによりできなかったので、
まずは和食の基礎を叩き込もうと和食の門を叩いたわけですね。
実は和食がベース
学校とはいえ、和食の世界は職人の世界。
周りは寿司屋や料亭で働こうという気合いの入ったやつらばかりです。
そんななか、将来は違うことをやろうと思っているやつが混じってきたわけですが、
皆さん懐深く、迎えてくれ、切磋琢磨しながら料理のいろはを学びました。
桂向きは3mを超え、研ぎを理解するため、菜切り包丁は一本研ぎ切りました。
ホテルの研修では、一度に100個の温泉卵を造るプロとして、重宝されたこともありました。
しかし今ではあの時のような、透けて見える大根の向こう側も、ピタッと決まった緩い卵を作る自信も毛頭ありません。笑
ガチイタリアンで研鑽を積む
そんなこんなで、卒業と同時に東京の某イタリアンに就職。
当時はパワハラ、激務のオンパレードです。
下積み時代は、顔以外はアザだらけという時代でございました。
しかし、そこで本当の料理や仕込みの基礎を学べたことに、感謝しています。
最近になってそのころの無茶が身体に響いているな・・・と感じることもありますが。笑
そんな修行に明け暮れる中、突如甲殻類アレルギーが発症。
自分で作った海老の味噌汁を、うまいうまいとむさぼっていたら、アナフィラキシーで呼吸困難になり、全身に発疹ができ、冗談ではなく死にかけました。
すぐ近くに病院があって、すぐにアドレナリン注射が打てたので、回復できましたが、そのままだったらどうなっていたのでしょうか。
もしかしたら、今こうやってキーボードをカタカタできていないかもしれませんね。笑
ホールサービスって面白い
アレルギーってのは一度発症すると戻らないんですね。
茹でた卵が、生卵に戻らないのと同じです。
海老の殻を炒めた蒸気だけで、疼くようになってしまったので、厨房を飛び出し、本格的にホールに出ることにしました。
まともに持ち場を持つ前に厨房を出ることになったのは今でも心残りではあります。
とはいえ、ホールも修行としてやっていましたので、そこまで抵抗なく始められ、むしろちょっと面白いかもと思い始めていたら、銀座のクラブ街のど真ん中の、某イタリアン兼ワインバーに配属になりました。
ワインっておもしろ
ここで大量のイタリアワインと触れ合うことになります。
銀座のクラブ街ですから、デイリーからそれなりのワインまでどんどん空きます。
ブルネッロのエレガントさ、
バローロの厳格さ、
フランチャコルタの細かく、エレガントな泡、
特にイタリアは地域ごとに全然違う品種で、
いったいどれだけの種類があるねん!
とツッコミたくなるようなバラエティーの豊かさに、
「ワインっておもしろ」
と思うようになりました。
この時に某資格も取ったりしましたが
それはどちらかと言えば
パワハラに対抗、見返すため
料理ができなくなったので、他のなにかで手に職をつけるためにとった部分もあり、
また言葉が持つイメージと
いま自分のやりたいことの乖離があるため、使うことはやめました。
もっと自由に、ワインの良さや楽しみ方を広めていきたいのです。
忙殺の日々
店長を任されたり
麻布十番の店舗に配属になったりで
激務の日々は続いていきました。
お客様にも気に入っていただいて
「将来店を出すなら、金を出すよ」なんて言っていただいたりもしていたので
それなりに頑張っていたんだと思います。
まあでも扱うのはイタリアワインだけだし、
それだけじゃあなかなかワインの本質は分からんということで
やっぱり悩んでいたんです。
そしたら叔父がワイン屋をやっていましたので、
レストランをやめて勉強させてもらうことにしました。
ワインって旨い
Noisy Wineにきて思ったのは
「ワインって旨い」
ってことでした。
それまでも様々なワインを飲んできましたが
とにかく全部うまかった。
それまでのワインとは
味わいのキラメキと
ツヤが全然違って
輪郭が明瞭。
そしてなぜか「旨い」。
その理由の一番は、温度管理でした。
当時のレストランはそれなりのグレードではあったものの
安いワインは常温保管。
当時はそんな店ばかりで、普通だったんですね。
それでも、それなりに旨かった。
でも「旨さのレベル」が違ったんです。
それはやはり、徹底した温度管理による
「ダメージを受けていないワイン」
の味わいだったんですね。
そしてどれも旨い。
これはある意味単純で、最も難しいんですが、
「旨いワインだけ」
をセレクションしているからだったんです。
なぜ「旨い」のかがわからない
とは言え、なぜ「旨い」のでしょうか?
当初はそこに明確な答えは見いだせなかったのですが、
毎晩Noisy家に入り浸ってテイスティングをしていく中で
徐々に見えてくるものがありました。
そして、「そこ」が分かったら将来的にワイン造りがしたいと思ってたんです。
でも「そこ」を追求するほどに、
日本でのワイン造りって限界があるんじゃないか・・とも思うようになってきてしまったんです。
(今は素晴らしい日本の生産者が増え、勉強不足だったなあと反省する日々です。)
それとやっぱり、料理をするためにこの世界に入り
休む暇なく走り続けていましたが
モチベーションの原点は
「いつか自分の店を出す。(料理人で)」
という部分のまま来てしまったんですね。
ワイン造りをしたい。
というのもワインという商材の中で、料理人に通ずる工程がそこだったからなわけで。
今までは頑張ってこれたけど、そこがなくなってしまうと自分の中の頑張るガソリンがなくなってしまったんですね。
アレルギーが出た後に、そのまましっかり自分と向き合わずにズルズルと来てしまったのも問題だったんだと、今は思います。
そこから燃え尽き症候群でなにもやる気が起きなくなってしまいました。
ニートの日々
そこからはモラトリアム人間として、ありきたりな行動パターンを取りました。
とりあえず旅に出ようと屋久島に行き、バイカーハウスで同じような若者たちと出会い、なにも考えずに北上してみたり。
香川で食った200円の素うどんのうまさに衝撃を受けたり。
海鮮にあたって、松山のビジホに何日もこもりっきりになったり。
まあでも心はどこか上の空で、結局帰ってきても身体と心がちぐはぐで、身体を全く動かせなくなってしまったんですよね。
布団から出れない。
目標が全くないから、布団を出て、なにをすれば良いかわからない。
だから行動ができない。
今考えればガチめの鬱だったんだと思います。
人間にとって目標って大事ですね。
どんなに小さくても、なにかの目標があることが、人が身体を動かす原動力なんだということをこの時に学びました。
布団の中から1、2月か経ったある日、気づきを得て、抜け出すことに成功します。
その答えとは・・・
「別になんでもよくね?」
ということでした。笑
地獄の就職活動
無事布団から抜け出し、ハローワークで就活を始めました。
そんな経緯ですから、仕事は何でもいいから受かったところで頑張ろう的な感じです。
これって凄く健全で、晴れやかな気持ちだったことを覚えています。
しかし専門卒の就活というのは本当に厳しいですね。
まず大半のところは受けられない、最低条件が大卒。
条件が良いほど、大卒じゃないと応募すら受け付けていない。
そんな中、なんとかかんとか数社内定も頂くことができました。
今までのキャリアと全く関係の無い業種もありました。
でもそんな中、自分の中のなにかが
「本当にそれでいいのか?」
と囁くのです。
まだまだ若造ではありますが、
「食に関わる」
ということが自分のアイデンティティなんだ、と本能的に察知したんですね。
本当にギリギリのところで、丁重に内定を辞退させていただきました。
改めて、「食に関わる」というところで就活を再スタートです。
しかしそこからはさらに地獄の日々。
やっぱり条件の良い会社は大卒じゃないと書類すら送らせてくれないし、
試食があったら、アレルギー発症するかもしれないからって食品系の企業は断られるし、
諦めかけてたら一社、話を聞いてくれました。
食品系の輸入商社です。
そこは社長が変わっていて、ワインの某資格を持っていてました。
私も某資格を持っていることに興味を持って頂き、その年齢で取れるなら頑張れるやつだ、と思っていただいたようです。
なんと面接の場で、採用して頂くことができました。
帰り道には、自然と涙が流れてきたのを覚えています。
就職活動を開始してちょうど1年が過ぎていました。
飲食あがりにサラリーマンはちょっとしんどい
これはもし、同じ境遇の人がいたら届いてほしいなと思うんですが、飲食あがりで普通のサラリーマンは本当に厳しいです。
なぜなら一般的な社会常識が備わっていないから。
厨房や店の中って本当に狭い世界なんですよね。
外の世界には、そこにはない常識がいっぱいある。
20代とはいえ、年齢的には新卒ではないので、当たり前にできると思われていることを、知らない。
このギャップにひどく戸惑いました。
もちろん、最初は凄く怒られました。
それはもうしんどいほどに。
飲食業だって立派な社会人です。
それなりにやってきたプライドがありました。
しかし、言葉使いや対応の仕方、客先での立ち振る舞いなど、飲食では気にすることすらなかったがとても大事になってくるんです。
この「常識」に脳内をインプットさせるのには随分苦労しました。
コツは「素直になる」と「今までのことは忘れて、一から勉強するつもりで頑張るです。」
でも飲食あがりってどんなに怒られても、
「あれ?」
って思うことがあるんです。
だってどんなに怒られても
「手が出てこない」んです。
これも外の世界では「当たり前」です。
輸入の仕事のいろはを学ぶ
そんな人間は結構タフに見られるみたいです。
必死こいて、輸入や関税の仕組みを勉強したり、現地とのやり取りのために英会話に通ったり、営業を頑張ったりしていたら少しずつ、仕事や常識を学んでいって、怒られなくなってきました。
そうすると、次第に色々と任せてもらえるようになります。
メインは肉の輸入の会社でした。
しかも小さい会社でしたら、畜種の数でいったら大手より多かったと思います。
様々な畜肉を扱いました。
肉だけではなく、本当にいろんな食材を輸入しました。
とある食材のブランドを立ち上げたりもしました。
そして、トラブルにも山ほど遭遇しました。
随分と修羅場にも立ち会い、鍛えられたと思います。
限界サラリーマン、ワインと再会する
そんなしんどいながらも、成長を感じられる日々を送っていたところ、それまでの仕事で最大級の山場を迎えます。
今でも忘れません。
それは、新年明けて、少し経った一月下旬頃、真冬の話です。
社長から引き継いだ数億円の仕事です。
それまでは順調に来ていましたが、突如今回で無くなるかもしれない、という状況に陥りました。
小さい会社ですから、柱の商売の一つです。
サラリーマンの方なら、これを聞いただけで胃がキュ~となる方も多いのではないでしょうか。
オイジーも商売をなんとか継続させるために、日中夜問わず、海外と交渉して、為替とにらめっこして、戦っていました。
しかし、上からのプレッシャーは相当なものです。
会社からも、毎日詰められます。
そんなこと言われたってやってるよ!と言いたくなるのをこらえ、(言ってしまったかもしれませんが笑)
何日もそのプレッシャーの中にいて押しつぶされそうだったんですね。
そんなある日の帰り道、とある量販店のワインが目に入ったんです。
「久しぶりにワインでも飲んでみるか・・・」
ワインの本当の効能を知る
既に会社でも中堅になっていましたから、就職してから4~5年は経っていたと思います。
その間お酒はたまに飲んでいましたが、ほとんどワインを飲んでいませんでした。
何の気なしに手に取ったそのワインは北米のカベルネ・ソーヴィニョン。
いっても3桁の、安いワインです。
ナチュラルワインやナチュール、自然派ワインと言われる類のものでも無い、普通の安ワインです。
しかし図らずも、そのワインに
「心から癒された」
のです。
なにも考えずに、
たまたま目についたから手に取って、
何の気なしに口に運んだワインの
優しく、柔らかい味わいが
プレッシャーに追い込まれた限界サラリーマンの心に
スッと寄り添い、
癒してくれたんです。
じんわりと心に染み入り、
再び立ち上がる勇気をくれ、
明日からまた難題に立ち向かう活力を与えてくれました。
ワインの味が変わった
そのおかげかどうかは分かりませんが、
その商売は首の皮一枚で繋がり
なんとかやり遂げました。
それからというもの、すっかりそのカベルネ・ソーヴィニョンにハマり
数ヶ月かけて、計30本は飲んだと思います。
安かったですし。
でもある日、気付くんです。
「あれ?美味しくないぞ?」
温度管理の重要性に気付く
なぜ味が変わったのか?
コロナ禍の、異様に人が少ない通勤の電車内で考えてみました。
そうすると、とある仮説に辿り着きました。
ワインを飲み始めたのは1月下旬です。
今は夏前の5月ごろ。
いくら西海岸で大陸内輸送のコストがかからないとはいえ、価格帯的にどうコスト計算しても、恐らくリーファーコンテナは使用していない。
倉庫も常温のはずだ。
1月下旬に店頭に並んでいたのは、恐らく売れ筋だからそんなに倉庫で在庫になっていないはずだ。
北米から日本までは、およそ2週間の船便。
輸入から直で店舗まで並んだとしても、12月末ごろの輸入のはず。
売れ筋で回っているとしたら、倉庫に長く置いて保管賃を取られたくないだろうし(価格も安いし、余計なコストはかけたくない)遅くとも2~3カ月前の輸入だろう。
と考えると最長でも10月ごろの輸入かな。
気温はそれなりに下がっている。
さらに幸いなことに、北米から日本への航路はほぼ同緯度で赤道を通らないから、冬なら船上もかなり寒い状況で輸入される。
売れ筋商品だから暖房の効いた店頭に並べてもすぐになくなっていく。
北米のカベルネ・ソーヴィニョンというしっかり目のワインだということもあり、仮に店頭でダメージを受けても短期間ならそこまでダメージを受けないかもしれない。
つまり、「奇跡的に温度のダメージを受けない条件が重なっていた」と予想されるんです。
だから美味しかった。
しかし5月に飲んだワインは恐らく
春になり温かくなり、船上でも、倉庫でも温かくなってきて温度が上がってしまった。
ゆえにダメージの蓄積が大きくなり、いくら北米のカベルネといえど
高温による熱が入り、味わいの崩壊を免れなかった。
つまり「温度の高い状況に置かれる時間が長くなってしまった。」
だからまずくなった。
まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、この考察にはめちゃくちゃ合点がいきました。
自分もちょうど北米からの輸入の商売をやっていただけに、リアルに肌感覚として実感できたんです。
その時にNoisy Wineの存在を思い出したんですね。
セレクションに好みの差はあるかもしれないが、
温度管理は徹底している。
ここで買えば、年中旨いワインを飲めるのか、と。
そんなこんなで
ワインに限界サラリーマンを癒し、勇気づける効果があるなんて、昔は思いませんでした。
でも周りに、ワインを飲んでいる人間ってほとんどいないんですよ。
オイジーと同年代かさらに若い世代の人間はアルコールすら飲まなくなっている。
飲んでもスーパーの安ワイン。
これってめっちゃもったいない。
もっと日常の中にワインを落とし込んでほしい。
質の良いワインは、明日への活力になるからです。
きっと今日もどこかで上司に、顧客に詰められ、ダメージを蓄積している社会人がいるはずです。
言ってもワインがその悩みを解決することはできないと思うけど、
多分寄り添ってくれることはできる。
「良質なワイン」は
張り詰めた気持ちを緩め、
癒し、
活力を与えてくれる。
ネガティブを少しポジティブに。
日常に彩りを与え、気持ちも晴れやかにしてくれる。
これって他のアルコールや飲料には無い効能だと思うんです。
だからワインを売ることにした。
社会で頑張るみんなを、
「良質なワイン」を届けることを通して
サポートしたい。
そんな気持ちの芽生えから、ワイン屋をやることにしました。
とはいえ、家庭も持ったので、不安定な商売に踏み入る決意をするのにそれから数年を要しましたが、結局はそういうことです。
そんな思いでワイン屋をやってますよ、ということを知っていただければ幸いです。
そしてこのサイトは
そんなワインを楽しむための様々な情報を
まとめていけたらと思っています。
ワインは飲んで味わうだけでも楽しいですが、
「情報を飲む」
なんて言われるほど、知れば知るほど面白いですからね。
では。


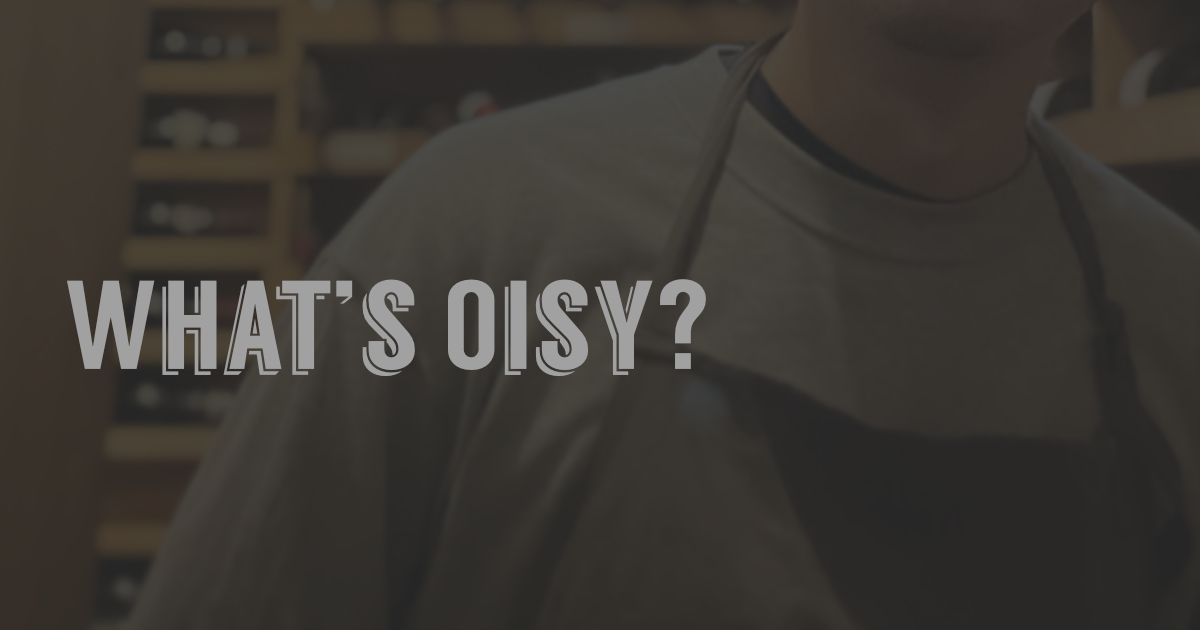

コメント